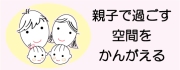「安全」-建築空間の日常安全を検証します
建築空間の安全性は地震や火災といった非常時だけの問題ではありません。むしろ日常的な状況で多くの事故が発生し、不幸にして傷害を負う方も少なくないのですが、その実態が正しく把握されていないこともあり、これまで見過ごされがちでした。
近年は、社会の成熟に伴って、人々の安全に対する意識が高まってきています。より安全な生活環境実現のために設計時、管理時において何をするべきか検証します。
【事故事例の収集と原因分析】
事故の事例を幅広く収集し、その原因を、人間行動の特性に着目して分析することにより、危険を回避するための空間デザインを提案します。
- ガラス事故事例収集分析
- 学校事故収集分析
? 「安全」-建築空間の日常安全を検証します
建築空間の安全性は地震や火災といった非常時だけの問題ではありません。むしろ日常的な状況で多くの事故が発生し、不幸にして傷害を負う方も少なくないのですが、その実態が正しく把握されていないこともあり、これまで見過ごされがちでした。
近年は、社会の成熟に伴って、人々の安全に対する意識が高まってきています。より安全な生活環境実現のために設計時、管理時において何をするべきか検証します。
【事故予防・データベースの開発】
事故は設計や管理に携わる人間の意識や知識によって防げるものが多いです。そのために必要な情報を分かりやすく整理し、実務に活用できるデータベースを開発します。
建物事故予防ナレッジベース
? 「快適」-利用者行動から空間をデザインします
近年は、ライフスタイルが多様化し、人々の行動も変化しています。空間もそれに合わせて計画されるべきですが、そのためにはその場所の特性に応じて人々の属性を整理した上で、行動や心理を細かく把握することが求められます。私たちはそのような心理・行動の正しい分析に基づいて、人々が快適に心地よく過ごせる空間をデザインします。
【親子で過ごす空間のデザイン】
今、子育て世代の行動や価値観は大きく変化しています。共働き家庭が増える一方で、父親も子育てに積極的に参加し、家族との時間を大切にし、小さな子どもを連れて積極的に街に出かけていくなどといった現象が見られます。このような変化の著しい子育て世代の生活スタイルやニーズを適切に把握し、快適で心地よい空間デザインを行います。
パパ・ママ・子供の視点から、
ここちよい空間デザインに
ついて考えるブログ
授乳室の研究・デザイン
乳児連れの外出時には必須の授乳室。ママ・パパ・赤ちゃん、家族みんなが心地よく使える授乳室を追求しています。子連れ家族の外出行動調査
子連れでお出かけしやすい街のつくりとはどういうものか、実態調査からニーズと要件を明らかにします。子育てファミリーの住まい方、ライフスタイル分析
社会背景によって刻々と変化する、子育て世代の生活時間や親子3世代同居のニーズを調査し、あるべき住まいについて分析しています。
? 「快適」-利用者行動から空間をデザインします
近年は、ライフスタイルが多様化し、人々の行動も変化しています。空間もそれに合わせて計画されるべきですが、そのためにはその場所の特性に応じて人々の属性を整理した上で、行動や心理を細かく把握することが求められます。私たちはそのような心理・行動の正しい分析に基づいて、人々が快適に心地よく過ごせる空間をデザインします。
【公共空間のユーザビリティ検証】
公共の施設や空間ではバリアフリー化が進み、ますます多様な人々によって利用されるようになっています。一方、そのような場所は大規模化、複合化、集客化する傾向にあります。つまり、大勢の利用者の細かいニーズに対応しなければならない状況が生まれています。行動パターンの異なる利用者属性と細分化されたニーズに応じた設備整備のポイントを求め、多様な人々にとって快適な空間づくりを追求していきます
? 「価値」-都市空間の価値を発見します
現在、都市を取り巻く社会環境が大きく変化しています。少子高齢化や人口減少により郊外のベッドタウンではコミュニティの崩壊が問題化している一方で、都心にはタワーマンションに高密度に人が集まり、防災上の安全性が指摘されていたりします。このような変化の中にあって、持続的な豊かな都市空間を創造するには、これまでの延長ではない新しい視点で、都市の価値を考えていく必要があります。
【都市居住者の意識・行動分析】
これまで、居住地域の価値を測る指標としては、通勤や買い物の利便性、公共施設の充実度など、いわゆる「用」の部分に重きが置かれていました。しかしながら、近くの広場でのびのびできる、知り合いと集える店が近くにある、安全安心に子どもを遊ばせることができる、などといった、必ずしも「用」だけでは測られない部分も、生活の質にとって大切です。我々は、都市生活者の意識レベルで地域の魅力について引き出し、新しい都市居住の価値を提案しています。
都市圏居住の価値を探る
評価グリッド法を用いたインタビュー調査により、都市生活者が感じている地域の魅力についての評価構造を明らかにし、地域の価値を測る指標を提案。
? 「価値」-都市空間の価値を発見します
現在、都市を取り巻く社会環境が大きく変化しています。少子高齢化や人口減少により郊外のベッドタウンではコミュニティの崩壊が問題化している一方で、都心にはタワーマンションに高密度に人が集まり、防災上の安全性が指摘されていたりします。このような変化の中にあって、持続的な豊かな都市空間を創造するには、これまでの延長ではない新しい視点で、都市の価値を考えていく必要があります。
【 「都市公景」の提案 】
ストック型社会への転換を踏まえ、都市の新しいあり方を考えていく時期が来ています。私たちは、都市の景観とは、そこに暮らす人々の営為の産物・結果であり、豊かな景観形成は豊かな生活環境につがなると考えています。そういった観点から、従来の個を重視した開発型まちづくりではなく、「パブリック(公)」を意識した調和的まちづくりを目指す概念としての「都市公景」を提唱し、その実現に向けた手法を検討しています。
東京生活ジャーナル
都市におけるまちづくりの第一線に立つ人々へのインタビューと現地レポートを中心に、生活者が自らのまちの価値(パブリックの意味)に気付き、それを高めていくための取り組みや手法を紹介しています。
【企業研修 プログラム開発・運営】
・利用者行動イメージトレーニング
利用者がどういう場所でどういう行動をするのか、どういう気持ちになるのかについて、図面上でイメージするためのトレーニング/ツールの開発を行います。
・都市デザインフィールドサーベイ
実際の街に出かけ、建築物などを観察しながら、設計者の意図や、街のコンテクスト、ユーザーの評価などについて解説し、デザインのあり方について考察します。
【講師派遣】
専門的知見と豊富な実務経験をもったメンバーが、講習会や講義の講師としてお伺いします。
小林美紀(東京工業大学 特別研究員)
テーマ:こどものための安心・安全な都市デザイン
対 象:学校関係者、保護者、マンション管理組合、自治会関係者、
建築デザイナーなど
こどもにやさしい都市デザイン
子どもの視点から、町を歩いてみると、今まで気付かなかった町の問題や魅力を感じます。例えば、歩道の凸凹した路面のテクスチャーは、ベビーカーや足の小さな子どもたちにとって歩きづらさを感じます。また、夏の日のアスファルトによる日射の照り返しは、背の低い子どもたちの方が強く感じます。こういった身近にあるバリアを取り除く「バリアフリーデザイン」や、誰にでも使いやすいように考えられた「ユニバーサルデザイン」、ユーザー参加型の「インクルーシブデザイン」について、具体的な事例を画像や音声で解説します。また、それらのデザインの基になっている「アフォーダンス」の理論について分かりやすくお話します。子どもたちや子育て世代にとって、やさしい都市デザインとはどういったものかについて、建物や都市設備(舗装、エレベータ設置など)の設計・整備のポイントと、町の中での人々のふるまい方や意識の持ち方の大切さについて語ります。
こどもを犯罪から守る町の条件
子どもがターゲットとなる犯罪が近年増加しています。犯罪を防ぐために、防犯カメラを設置したり、死角をつくる茂みを伐採したり、犯罪意欲を抑える青色の街路灯を設置するなどの試みがとられるようになりました。防犯のためには、犯罪が起こる前の予兆を見逃さないことが大切です。そこで、なぜか勝手にゴミが捨てられる場所、落書きされやすい場所などの特徴を解説し、それを放置すればどうなってしまうのか、またどのような改善策があるのかについて、具体的な事例を挙げながら説明していきます。そして、子どもたちにとっても安全で安心して遊べる地域をつくるために、どのような学校、公園、住宅のデザインが求められるのかを説明します。また、子どもたちを守る上で重要な役割を果たす、人と人とのつながり、コミュニティ、地域活動のあり方についてもお話します。
町の感性を養う「サンドスケープ」と「スメルスケープ」
子どもたちは、道端に立ち止まって花の香りを感じたり、踏切や電車の音に耳を傾けたりするなど、大人になると見逃してしがいがちな町の風景や香り、音に対する高い感受性を持っています。目で見て感じる景観だけでなく、音や香りを積極的に感じることは、イメージを膨らませたり想像力を伸ばしたりすることに寄与します。もちろん騒音や悪臭などの環境や健康を壊していく要素はうまくコントロールしなければなりません。そういったマイナス面やプラス面を含めて、町のなかにあるスメルスケープ(香り風景)やサウンドスケープ(音風景)を五感を働かせて感じ取っていく術を伝授します。身体全身で町を体験することで、
添田昌志(LLP人間環境デザイン研究所)
テーマ:移動空間のデザインを考える
対象:建築デザイナー、エクステリアデザイナー
シークエンスデザイン
名庭と言われる日本庭園や美しい街路空間には優れたシークエンスがあります。美しい景観とは何か、「移動」する人の視点をキーワードにポイントとなる空間構成のあり方を語ります。
wayfindingデザイン
利用者が目指す場所にスムーズに移動できることは空間が備えるべき最低限の性能です。分かりやすい街や施設を作るポイント(空間構成・サイン計画など)について、様々な研究成果と実際の事例を元に解説します。
仲綾子(仲建築研究所)
テーマ:こども病院の計画・設計
対象:医療・看護・教育・保育に関わる方々・患児の家族・設計者など
こどもが育つ場としてのこども病院のつくり方
病院は、医療空間であると同時に、入院するこどもたちにとっては生活空間ともなります。こどもたちが治療を受けつつ生活する場として病院はどうあるべきか。病院におけるこどもたちの行動を詳細に調査・分析した学術研究にもとづき、こどもが成長・発達する場としてふさわしいこども病院のつくり方について提言します。
病院における屋外空間の重要性
光、風、空、雲、木立、草花、せせらぎ、、、屋外空間は、ともすれば単調になりがちな入院生活に変化を与えてくれます。たとえ外出できなくても、窓から眺めることができる風景は重要です。こうした屋外空間のあり方について国内・海外の事例などをもとに解説します。
若林直子(有限会社生活環境工房あくと)
テーマ:防災、コミュニティ、まちづくり
対象:一般市民、町会・自治会、企業、マンション管理組合・管理者、
学生、行政関係者等
安心安全のための地域のネットワークづくり
大地震の被災地の映像や各地の事例、学術的な研究成果などを交え、いざというときに心強い地域のネットワークや今の時代にあった対策のあり方などについて提言します。また、その地域の特性に合わせて、いざというときに暮らしはどうなるのか、事前にどのような計画・対策が必要かについても分かりやすく解説します。
防災ワークショップ 被災生活机上体験
「巨大地震が発生、地域の学校に被災した人々が集まってきて自然発生的に避難所となった。その3日後、大混乱する避難所で避難所運営組織を自主的に立ち上げようと有志(=受講者)が立ち上がった」等の想定でワークショップを行い、被災生活の大変さ、避難所運営等の防災計画の重要性、計画づくりのポイント、合意形成手法(スキル)等を体感していただきます。
まちの防災チェックをしよう! 地域の防災探検会
まち歩きのワークショップです。各自、自由にまちを歩き、防災の視点から気になるところを見つけてカメラで撮影し、気になった理由等を自由にコメントしてもらいます(キャプション評価法)。個人の視点を持ち寄って、参加者みんなでその地域の防災環境について話し合います。 なお、「防災」だけでなく、「防犯」「景観」「コミュニティ」などのさまざまな視点でも実施しています。